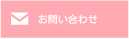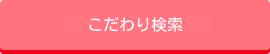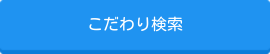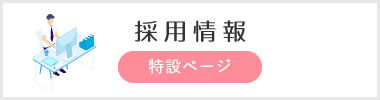TOPICS&BLOG
ブログ記事
賃貸事務所と賃貸住居の違いとは? SOHOについても解説
フリーランスや個人事業主にとって「住まい」と「仕事場」をどう分けるかは悩ましいテーマです。中には自宅をそのまま事務所として使いたいと考える方もいるでしょう。しかし、賃貸事務所などの事業用賃貸物件と居住用賃貸物件では、契約条件や法的な取り扱いが大きく異なります。
本記事では、事業用賃貸物件と居住用賃貸物件の違いを分かりやすく解説するとともに、自宅を仕事場として活用できる「SOHO(ソーホー)」という選択肢についても詳しくご紹介します。用途変更のリスクや注意点も踏まえて、自身に合った働き方を見つけましょう。
賃貸事務所と賃貸住居の違い
賃貸事務所(以下「事業用賃貸物件」)と賃貸住居(以下「居住用賃貸物件」)は、さまざまな点で違いがあります。ここからは、それぞれの違いについてご紹介します。
使用目的の違い
そもそも、居住用賃貸物件は借主が生活するために契約するのに対し、事業用賃貸物件は事業を行う人(テナント)がビジネスや商売をするために契約するものです。事業用賃貸物件の場合、不特定多数の人の出入りが想定される他、居住用賃貸物件よりも建物や設備の傷みが早いという特徴があります。
契約にかかる費用の違い
事業用賃貸物件は居住用賃貸物件と比較して、初期費用が高くなる傾向にあります。これは、事業用賃貸物件の賃料自体が高く設定されているため、それに伴い敷金や礼金、仲介手数料なども高額になるためです。
特に保証金(敷金)は、事業がうまくいかない場合の賃料滞納リスクを考慮し、居住用よりもかなり高額(賃料の3〜10カ月分程度)に設定されるのが一般的です。
なお、居住用賃貸物件の賃料は非課税ですが、事業用賃貸物件の賃料には消費税が課税されます。ただし、敷金などの預り金は非課税です。
法的保護と契約内容の違い
生活のために利用される居住用賃貸契約の場合、消費者契約法によって借主が不利な契約を結ばないように保護されます。一方で、事業用賃貸契約の場合、法的保護が適用されません。そのため、事業用賃貸契約では契約内容をより慎重に確認する必要があります。
退去時の解約予告期間も異なり、居住用賃貸契約が一般的に1〜2カ月前であるのに対し、事業用賃貸契約は3〜6カ月以上前と長く設定されているのが一般的です。
事業用賃貸契約では、契約期間内に即時解約した場合や、オーナーの許可なく転用した場合に違約金が発生する旨が明記されていることが多いです。また、賃料滞納や信頼関係の破綻、近隣トラブルなどが起きた場合、状況によっては契約解除となることがあります。
入居審査基準の違い
事業用賃貸物件と居住用賃貸物件で、入居審査の基準も大きく異なります。居住用賃貸物件では個人の支払い能力が重視されますが、事業用賃貸物件では事業の内容や規模、売り上げ、そして事業計画の妥当性などが厳しく審査されます。場合によっては詳細な事業計画書の提出も必要です。
退去時の原状回復に関する違い
退去時の原状回復義務は居住用賃貸物件、事業用賃貸物件ともに存在します。ただし一般的に居住用賃貸物件については「通常の使用による損耗」や「経年変化」については、借主が原状回復義務を負いません。
なお、事業用賃貸物件は人の出入りが多く損耗しやすいという特性から、特約によって借主の負担範囲が詳細に明記されているケースが多いです。契約締結時には、修繕費用を負担する範囲を確認しておくことが重要です。
賃貸住居を事務所として使えるか?
「自宅のマンションやアパートを、そのまま事務所として使いたい」と考えるフリーランスの方もいるでしょう。結論から述べると、契約上は原則NGです。多くの居住用賃貸契約書には「住居以外の目的利用は禁止」と明記されており、このような物件を無断で事務所として利用すると契約違反となります。発覚した場合、最悪は契約解除・強制退去を求められるリスクがあります。まずは今借りている物件の契約書を確認し、「使用用途:居住用」「事務所利用禁止」などの条項がないかチェックしましょう。
居住用賃貸物件の事務所利用は原則禁止
マンションなどの賃貸物件では、管理規約や賃貸契約で「住むことだけを目的として使う」と決められているのが一般的です。特に居住用として契約している集合住宅では他の入居者の生活環境を守るため、無断で事務所に転用してはいけません。例えば、自宅でひっそりパソコンで事務作業をする程度なら分からないかもしれませんが、来客が増えたり荷物の集配が頻繁になったりすると周囲にすぐ知られてしまうでしょう。人の出入り増加や騒音は近隣トラブルの原因となり、オーナーにも迷惑をかけてしまいます。
賃貸借契約に違反して勝手に事務所として利用すると、契約違反と見なされ、契約を解除される可能性があります。違約金や、残りの契約期間分の家賃を請求されるケースもあるため、トラブルを防ぐためにも無断での転用は避けましょう。
事務所利用可物件やオーナー許可が得た物件の場合は例外
どうしても住居で仕事をしたい場合は、例外的に事務所利用が認められている物件を探すか、オーナーに個別相談して許可を得る必要があります。募集条件に「事務所可」と記載のある賃貸物件であれば、契約上住居と事務所の兼用が可能です。このような物件はマンションでも一部あり、特に都心部では「SOHO向け」などと称して募集されることがあります。
もし現在住んでいる物件が居住専用でも、オーナーと交渉して事務所利用を認めてもらえるケースもゼロではありません。ただしオーナー側にはデメリットも多いため、簡単ではありません。事務所利用を認めるとオーナー自身の負担する税金(固定資産税や所得税、消費税)の扱いも不利になる上、他の入居者とのトラブル対応など管理上の負担も増えます。そのためよほど人の出入りが少ない業種(例:在宅で完結するIT業や作家業など)でない限り、許可は下りにくいのが現状です。相談する場合は事業内容を具体的に伝え、迷惑をかけない旨を丁寧に説明しましょう。
契約違反による法的なリスクにも注意
「バレなければ大丈夫だろう」と、無断で住居を事務所にしてしまうことは避けましょう。例えば、居住用賃貸物件において不特定多数の来客を伴う営業行為を行うと、都市計画法上の用途地域に抵触する可能性があります。用途地域とは、その土地でどのような建物を建ててよいかが決められたもので「住居系」や「商業系」といった区分があります。住居専用地域では、原則として事務所や店舗としての利用は認められていません。
万が一、無許可で違法な事業を行っていると見なされれば、行政指導や是正勧告を受けることも考えられます。オーナーにとってもリスクであり、発覚すれば即刻契約解除となるでしょう。
どうしても自宅を事務所として使いたい場合は「事務所利用可」の物件に引っ越すか、オーナーの許可を正式にもらって契約内容を変更する必要があります。安易な無断転用は避け、契約ルールを守るようにしましょう。
SOHO(ソーホー)とは?
「SOHO(ソーホー)」とは「SmallOffice/HomeOffice」の略で、自宅兼事務所のように住居と仕事場を兼用する働き方・物件形態を指します。
先述の通り、本来住居契約物件は事業利用が禁止ですが、中には「SOHO可」といって住まいとして使いながら仕事にも利用できる物件があります。「SOHO物件 = 住居契約」「オフィス物件 = 事務所契約」という点がポイントです。つまり、SOHO可の賃貸物件では契約形態自体は居住用賃貸契約ですが、「そこに住むこと」を前提としつつ一部事務所利用が認められているのです。
SOHO物件のメリットとして、住居契約ならではの恩恵が受けられる点が挙げられます。例えば、家賃に消費税がかからないことや夜間に寝泊まりできること、住居としての設備が整っていることなどが挙げられます。個人事業主の場合、家賃などの費用を按分(あんぶん)計算して事業経費に計上することも可能です。按分とは自宅兼事務所利用時に、家賃や光熱費のうち仕事に使った分だけを経費として計上する手法です。
一方でSOHO物件には、デメリットもあります。居住用賃貸契約であるため法人登記や看板設置ができない場合が多いこと、間取りや回線設備がビジネス用途に適していないこと、他の居住者への配慮から不特定多数の来客を伴う業務はできないことなどです。
SOHO物件は「住まい」が主な用途であり、その一部を仕事用として活用できる物件だと考えるとイメージしやすいでしょう。他の入居者はあくまで普通の生活をしている人々なので、ビジネス色が強過ぎる使い方(例:人の出入りが多い、騒音が出る、物品販売するなど)は認められません。逆に、在宅プログラマーやデザイナー、ライターのように一人でパソコン作業が完結する業種にはSOHO物件は理想的といえます。
まとめると、SOHOとは「住居契約で借りた部屋を、居住しながら仕事場としても使うこと」です。完全なオフィス契約とは異なり制約もありますが、家賃負担を抑えつつ自宅でビジネスができる選択肢として注目されています。もし自宅をSOHO化したい場合は、先述の通りオーナー許可が必要です。物件探しの際には「SOHO可」「事務所相談可」と記載のある物件を選ぶようにしましょう。将来的に法人登記が必要になったり来客が増えたりすることが見込まれるなら、本格的な事務所契約物件への移行も検討するとよいでしょう。
住居と事務所を兼用・転用する際のチェックポイント
最後に、賃貸物件を居住用から事業用に転用・兼用する場合の注意点・確認事項をご紹介します。フリーランスの方が自宅兼事務所とする際に、以下のポイントをチェックしてください。
賃貸契約書・管理規約の確認
まず契約上、事務所利用が許されているかを確認します。マンションなら管理規約にも「居住専用」「事務所利用可」などの定めがあります。契約で禁止されていれば無断で用途を変更してはいけません。
用途地域の確認
借りている物件の所在地が都市計画法上、どの用途地域かを調べましょう。例えば、第一種低層住居専用地域などでは、事務所や店舗としての利用が厳しく制限されています。行政上の問題がないかを事前に調べ、必要なら役所や専門家に相談しましょう。
オーナーへの事前相談・許可取得
住居を事業用途で使いたい場合、事前に貸主(オーナー)に相談し許可を得る必要があります。口頭了承だけではなく、できれば書面で「住居兼事務所利用を承諾する」旨の同意をもらい、契約書に特約として残しましょう。勝手な転用はNGです。
法人登記・営業許可の可否
賃貸住宅の住所を会社の登記住所に使いたい場合、契約内容を確認し、その使用が認められているかどうかを確認しましょう。多くの居住用賃貸契約では法人登記を禁止しているケースがほとんどです。どうしても登記したい場合は、事務所契約物件を借りる方が無難です。
加えて、業種によって必要な許認可(例:古物商許可や美容院の開業届など)をその住所で取得できるかも確認しましょう。オーナーから承諾書を求められる場合もあります。
近隣への配慮
自宅兼事務所とするなら、今まで以上に近隣への配慮が欠かせません。他の住民に迷惑をかけない業務範囲にとどめ、騒音や頻繁な来客・宅配便の増加などトラブルの原因を極力避けましょう。在宅勤務であっても集合住宅では共同生活の一員であることを意識することが大切です。
経費・税務処理の区分
住居兼事務所にする場合、家賃や光熱費を事業経費に落とす際は家事按分が必要です。どのくらいの面積・時間を仕事に使っているか合理的な基準で按分計算し、税務処理しましょう。全額を経費にすることはできないので注意してください。
以上の点をしっかり確認し、トラブルのないよう準備を進めれば、賃貸住居であっても一定範囲で事務所的に活用することは可能です。ただし繰り返しになりますが、契約違反となる使い方だけは避けるようにしましょう。
まとめ
ここまで賃貸事務所と賃貸住居の違いを、利用目的・契約内容・コスト面から詳しく解説しました。居住用賃貸物件は生活の場、事業用賃貸物件は仕事の場として位置付けが異なり、それに伴って法律上の保護や契約条件、必要な費用も異なります。また自宅を事務所代わりに使う際は、さまざまなリスクがあるため、SOHO物件を選ぶのも選択肢の一つです。
フリーランスの方にとって、仕事場選びは働き方やコストに直結する重要なポイントです。ぜひ本記事の内容を参考に、ご自身のビジネススタイルに合った環境を整えてください。住居と事務所、それぞれの特徴を正しく理解し、快適かつ法律に即したワークスペースを実現しましょう。
オフィス賃貸の総合窓口では、大阪府や京都府、兵庫県、東京都の賃貸オフィス・貸事務所の物件情報を多数掲載しています。エリアや賃料はもちろん、「SOHO利用可」といったこだわり条件でも検索が可能です。理想の働き方を実現するため、ぜひオフィス賃貸の総合窓口を活用してみてください。
エステートエージェンシー