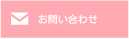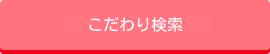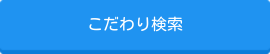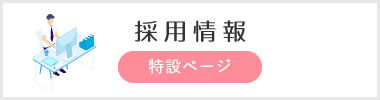TOPICS&BLOG
ブログ記事
ウェルビーイングを高めるオフィス環境とは? 設計のポイントを解説
ウェルビーイングを高めるオフィス環境は、従業員の健康や快適さを支えるだけでなく、生産性や企業イメージの向上にも直結します。本記事では、ウェルビーイングの基本や注目される背景、自然光や快適な空調、人間工学家具、リフレッシュ空間など設計の工夫を解説し、企業が取り組むべきポイントを紹介します。
「ウェルビーイング」という言葉は、単なる身体的な健康の維持にとどまらず、精神的・社会的にも満たされた状態を指します。近年は働き方改革やコロナ禍を経て、働く人の幸福や心の豊かさに注目が集まっています。
この記事では、ウェルビーイングの基本的な定義や注目される背景、企業が取り組むべきオフィス環境の工夫について解説します。さらに、導入事例や今後の展望も整理し、総務・人事担当者が自社のオフィス環境改善を考える際に役立つポイントを紹介します。自社のオフィスづくりや働き方の見直しにぜひ生かしてみてください。
昨今注目される「ウェルビーイング」な働き方とは?
1946年に策定された世界保健機関(WHO)憲章で初めて登場した言葉である「ウェルビーイング」ですが、近年では日本でもこの考え方が注目されています。特に働き方の分野で注目されており、その背景には複数の社会的要因があります。働き方改革による労働環境改善の推進、コロナ禍をきっかけとしたテレワーク普及、少子高齢化に伴う労働人口の減少などです。これらの変化により、従業員一人ひとりが心身ともに健康で、長く活躍できる職場づくりが不可欠になりました。
また、価値観の多様化に伴い、個人の幸福度や充実感を重視する意識が高まっています。ウェルビーイングはこうした流れに合致し、組織の生産性向上や人材定着率の改善につながると考えられています。企業にとっては「なぜ今ウェルビーイングが重要なのか」を理解し、働き方の見直しに取り入れることが大きな課題となっています。
ウェルビーイングを意識したオフィスの3つのメリット
ウェルビーイングを重視したオフィス設計は、従業員の働きやすさだけでなく、企業全体に多くの利点をもたらします。代表的なものとして「エンゲージメントの向上」「生産性や創造性の向上」「企業イメージの向上」の3点が挙げられます。これらのメリットは、人材確保や組織力の強化といった現代のオフィスに欠かせない要素です。
エンゲージメントが向上する
ワークエンゲージメントとは、仕事に対して「熱意」「没頭」「活力」の3つがそろった心理的状態を指します。ウェルビーイングを意識したオフィスは、従業員が安心して能力を発揮できる環境を提供するため、こうしたエンゲージメントの高まりに直結します。
例えば、リラックススペースの設置や柔軟な働き方制度は、従業員の心身の負担を軽減し、集中しやすい環境を生み出します。働きやすい職場は居心地の良さを生み、自然と帰属意識を強め、同僚との人間関係も円滑になります。結果として、仕事への熱意や没頭感が高まり、組織全体の活力につながります。
さらに、エンゲージメントの高い社員は離職率が低い傾向があるため、人材の定着や育成においても効果的です。企業がウェルビーイングに配慮することは、従業員と組織の双方にとってメリットの大きい取り組みといえるでしょう。
生産性や創造性が向上する
心身の健康が保たれた状態は、業務に集中する力を高めます。快適なオフィス環境は、ストレスや疲労を軽減し、従業員がバランスの取れた状態で仕事に取り組める基盤を整えます。
また、偶発的な交流が生まれるような空間設計は、創造性を刺激します。例えば、フリーアドレスやコラボレーションスペースの導入は、部署を超えたコミュニケーションを促進し、新たな発想を得るきっかけとなります。このような環境は、単なる効率性の向上にとどまらず、組織に新しい価値を生み出す可能性を広げます。
創造性が高まることは、イノベーションを生み出し、企業の競争力強化に直結します。ウェルビーイングを意識したオフィスは、生産性と創造性の両面を支え、企業が持続的に成長するための土台となります。
企業イメージが向上する
ウェルビーイングへの取り組みは、社外への発信力や企業ブランドの向上にもつながります。従業員を大切にする姿勢が明確になることで、求職者から「社員のことを考えてくれる会社」という好印象を持たれやすくなり、優秀な人材の確保に役立ちます。
また、働きやすいオフィス環境は従業員の離職防止にも効果を発揮します。心身の不調を抱える従業員を早期にサポートできる体制が整えば、安心して長く働ける職場という評価を得やすくなります。
さらに、SDGsやESG投資といった社会的潮流と結び付けて評価される点も大きな魅力です。持続可能な経営を意識した企業姿勢として認知されることで、社会的信頼の獲得やブランド力の強化につながります。ウェルビーイングを重視したオフィスづくりは、企業価値を高める経営戦略の一環として重要な意味を持っています。
ウェルビーイングを高めるオフィスをつくるポイント
ウェルビーイングを重視するオフィスづくりには、従業員が健康で快適に働ける空間設計が欠かせません。こうした環境は生産性や人材定着にも直結するため、企業にとって重要な投資といえます。ここからは「健康」「快適性」「働きやすさ」を支える具体的な工夫を紹介します。
健康をサポートする工夫
ウェルビーイングの基盤は「健康」にあります。従業員が心身ともに健やかに働くためには、身体的な負担を軽減するオフィス環境が必要です。例えば、長時間の着座による不調を防ぐ工夫や、自然光や空調による快適な環境整備は、生産性向上にもつながります。
また健康経営の観点からも、企業が従業員の健康を支援することは重要です。オフィス環境の改善は、働きやすさを高めるだけでなく、離職防止や長期的な活躍にも寄与します。
自然光を取り入れる
自然光を取り入れたオフィスは、従業員の心身に多くの良い影響を与えます。太陽光は体内リズムを整える働きがあり、睡眠の質や日中の集中力を高める効果が期待できます。また、自然光のある空間はストレスを和らげ、気持ちをリフレッシュさせる役割も果たします。
採光を工夫する方法としては、窓際にデスクを配置したり、吹き抜けを活用して明るさを確保することが挙げられます。さらに、窓から緑が見える席や、オフィス内に植栽を取り入れることで、視覚的な癒し効果も得られます。
このように自然光を活用した設計は、従業員が快適に働ける環境づくりに直結し、心地よさと生産性を両立する有効な取り組みです。
快適な空調と空気質を確保する
オフィスの空調や空気質は、従業員の集中力や健康に直結します。適切な温度や湿度が保たれていない環境では、疲労や不快感が蓄積しやすくなります。そのため、個別に調整できる空調や、換気による空気の循環が重要です。これらは感染症対策にも役立ちます。
さらに、空気中の花粉やPM2.5、VOC(揮発性有機化合物)などへの配慮も欠かせません。フィルターや浄化機能を備えた設備を導入することで、従業員が安心して業務に集中できる環境を整えられます。
また、オフィス内の騒音や空気のよどみを減らす工夫も大切です。静かで清浄な空気環境は、快適性を高めるだけでなく、心身の健康維持や長期的なパフォーマンス向上につながります。
人間工学に基づくデスクやチェア
長時間のデスクワークは、姿勢の固定化や身体の負担につながります。そのため、人間工学に基づいたデスクやチェアを導入することは、従業員の健康を守る上で有効です。上下昇降式のデスクを取り入れることで、立ち座りを切り替えながら作業でき、むくみや疲労、眠気の抑制、腰痛軽減といった効果が期待できます。
また、背もたれの角度や座面の高さ・奥行きを調整できるタスクチェアは、一人ひとりの体格に合わせやすく、快適な座り心地を実現します。これにより、身体への負担が減り、集中して仕事に取り組める環境づくりにつながります。
海外の先進オフィスでは、こうした人間工学的な家具の導入が一般的になっており、健康配慮と生産性向上を両立させています。日本でも、姿勢改善や疲労軽減に取り組むオフィス設計の一環として広がりを見せています。
働く活力を生むための工夫
従業員が「ここで働きたい」と感じられる環境は、働く活力を高める大きな要因になります。癒しや楽しさを感じられる空間があることでモチベーションが維持され、生産性や組織全体の活力にもつながります。ここでは、そうした工夫の具体例を紹介します。
リフレッシュスペースを設ける
オフィス内に休息やリフレッシュの場を設けることは、従業員の心身の健康を支える大切な要素です。仮眠スペースやリラックスできる休憩室は、疲労を和らげ、気分転換につながります。その結果、集中力や生産性が回復し、効率的に業務を進められる効果が期待されます。
また、カフェスペースを備えたり、照明に暖色系を採用したりすることで、従業員が自然と集まりやすい雰囲気をつくることも可能です。さらに、周囲の視線や騒音を遮る設計を取り入れれば、安心して休める環境が整います。
海外のオフィスでは、リラクゼーションルームや軽い運動ができるスペースを設ける取り組みも増えています。こうした工夫は、従業員が心地よく働き続けるために有効な手段といえるでしょう。
自然を取り入れる
オフィスに自然の要素を取り入れることは、従業員の心身に良い影響を与えます。観葉植物やフェイクグリーンを設置すると、リラックス効果やストレス緩和が期待され、幸福度向上にも寄与します。さらに、緑が視界に入ることで眼精疲労が軽減され、快適に働ける環境が生まれます。
自然のある空間は、従業員同士がリラックスして会話できる雰囲気をつくり、コミュニケーションの活性化にもつながります。バイオフィリックデザインのように自然を積極的に取り込んだ設計は、海外オフィスでも注目されています。
オフィスのどこにいても自然の癒しを感じられる環境は、従業員の活力を高め、組織全体のパフォーマンス向上にも貢献するでしょう。
コミュニケーションを促進する工夫
オフィスのデザインは、従業員同士の交流を促す重要な役割を担います。健全なコミュニケーションが生まれる環境は、信頼感や一体感を高め、エンゲージメントの向上にもつながります。さらに、対話が活発になることで新しい発想や協働が生まれ、イノベーションを促進する基盤となります。ここからは、その具体的な工夫を見ていきましょう。
共用エリアを設ける
共用エリアは、従業員同士の交流を自然に生み出す仕組みとして効果的です。落ち着いて相談できる対話スペースや、チームで作業できるグループワーク空間は、日常的な会話や情報共有をスムーズにします。また、カフェスペースや共創空間を導入することで、部署を超えた偶発的な出会いや交流が生まれ、新しい価値観やアイデアに触れる機会が増えます。
さらに、海外の先進オフィスでは、共用エリアを活用したワークショップやイベントを定期的に行う事例もあり、チームの垣根を超えたコミュニケーション活性化に寄与しています。社内イベントや休憩時間の利用シーンを通じて、共用エリアはメンバーの絆を深め、職場全体の信頼関係を強める場となります。
フリーアドレスを採用する
フリーアドレスは、従業員が固定のデスクを持たず、その日の業務内容や気分に合わせて働く場所を選べるスタイルです。この仕組みにより効率的な作業がしやすくなり、気分転換によるモチベーション向上も期待できます。さらに、部署や役職を超えて席が入れ替わることで、自然なコミュニケーションが生まれ、人間関係の構築にもつながります。
近年は、フリーアドレスを進化させたABW(Activity Based Working)が注目されています。オフィスに限らず自宅やカフェなど多様な場所を選択できるABWは、通勤時間削減や育児・介護との両立、趣味の時間確保など、従業員のライフスタイルに合わせた柔軟な働き方を実現します。
ただし、自由度が高い一方で、集中スペースの確保やITツールとの連携(席予約システムやオンライン会議環境の整備)といった工夫が必要です。こうした環境を整えることで、フリーアドレスやABWはコミュニケーションと生産性の両立に大きく寄与します。
まとめ
本記事では、ウェルビーイングの基本的な定義から、オフィスづくりにおける具体的な工夫までを解説しました。ウェルビーイングとは、病気がない状態を超え、心身ともに健康で社会的にも満たされた状態を意味します。近年注目を集める背景には、働き方改革やコロナ禍を経た価値観の変化があり、従業員一人ひとりの幸福度を高めることが企業の成長にも直結すると考えられています。
記事内で紹介したように、自然光や快適な空調、人間工学に基づいた家具、リフレッシュスペースや自然要素の導入は、従業員の健康を守りながら集中力や創造性を高めます。また、共用エリアやフリーアドレスといった仕組みは、コミュニケーションの活性化やエンゲージメント向上につながり、結果として企業のブランド力や採用力を高める効果も期待できます。
オフィス環境改善は単なる設備投資ではなく、人材の定着や企業価値の向上につながる長期的な取り組みです。これからオフィス移転や改善を検討する際には、専門的な知見を持つパートナーに相談することが大きな助けとなります。賃貸オフィス物件を多数取り扱う「オフィス賃貸の総合窓口」では、企業のニーズに合わせた物件選びをサポートしています。ぜひ従業員のウェルビーイングを向上させるようなオフィスを見つけるために役立ててください。
エステートエージェンシー